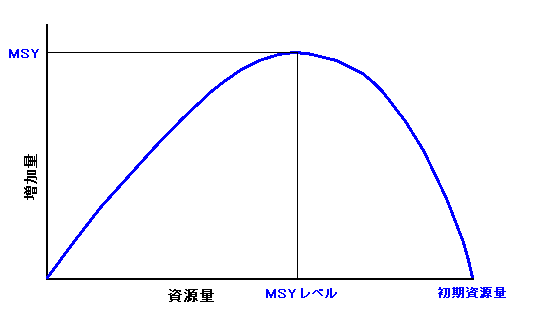
鯨や魚など水産資源の捕獲枠を決める際の重要な概念が「最大持続生産量(Maximum Sustainable Yield - MSY)」というもので、これは今現在のIWCの捕獲枠算定方式である改訂管理方式(Revised Management Procedure - RMP)や70年代半ばに採用された新管理方式(New Management Procedure - NMP)を理解する上で欠かせない。 そこで、この概念について簡単に解説しておく。
今、ミンククジラの集団があるとする(別に他の鯨種であっても、魚類であってもいいのだが)。 人間がこの集団から捕獲しない場合、環境の激変などがないかぎり、頭数はだいたい一定である。 この時の頭数を初期資源量という(環境が許容する最大限の量という事で「環境収容量」という言葉もある。 これは当然、環境の変化に応じて時間的に変わるから、初期資源量は「捕獲開始直前における環境収容量」といってもよいであろう)。 これは、この集団で毎年死ぬクジラと生まれてくるクジラの頭数がだいたい釣り合っている事を意味する。 仮に最初の頭数を10000頭として、毎年300頭が自然上の理由で死に(シャチなどの天敵に襲われる場合も含む)、300頭程度が生まれているとする。 さて、この集団から何年か捕獲を続けて頭数が6000頭に減ったとする。 この時、自然上の理由で死ぬ頭数と新しく生まれる頭数は釣り合っているだろうか?
このような状況に関する数多くの野生生物の研究で、新しく生まれる頭数の方が自然死するものより多い事が知られている。 一種の法則のようなものである。 これは、マクロの視点から見ると、あたかも集団が頭数を元に回復しようとしている一種の防御機能のように見えるが、ミクロというか個体レベルの視点では頭数が減る事によって群れの密度が減少し一頭当たりの餌の量が増えたりストレスも減るなど、繁殖を促進する要素が効いてくるためである。 このような回復力があるからこそ、過去に過剰に捕獲した鯨種も、捕獲をやめればだんだんと資源量が回復してくるわけである。 ただし、ものごとには限度というものがあり、あまり頭数が減ってしまうと回復も難しくなる(極端な話、数10頭まで減ってしまうと思わぬ災害で全滅する可能性もでてくる)。 この様子をグラフで簡単に表すと下図のようになる。 横軸が集団の頭数で、縦軸が頭数の自然増加分(= 生まれる頭数 - 死ぬ頭数)である。 この曲線のピークに対応する増加分をMSY(最大持続生産量)といい、その状態になる頭数をMSYレベルといい、初期資源量の50%から70%程度の場合が多いようである。
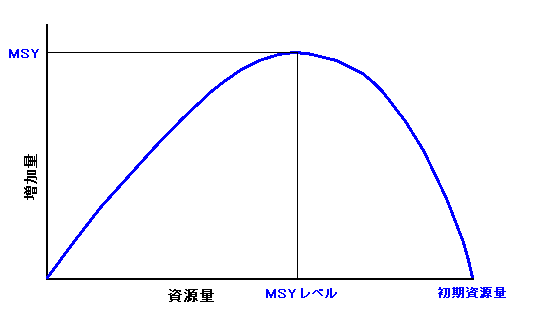
さて、10000頭いたクジラの集団のMSYレベルが7000頭であり、捕獲によって現在7000頭にまで減って、毎年410頭が生まれて200頭が死んでいるとする(数値はあくまで例えである)。 この状態では余剰分は 410-200、すなわち翌年までに210頭増える事になる。 「MSYレベルが7000頭」という事は、頭数が6000頭や8000頭の場合でもさらに増加はするが、毎年の増加分は頭数が7000頭の場合の210よりは少ない、というわけである。 さて、ここでこの集団から捕獲しなければ、翌年には頭数は7210頭に増えるが、もしここで210頭捕獲すると、来年までに増えているはずの頭数はまた7000になり、同じ状況がくりかえされて、410頭生まれて200頭自然死し、翌年また210頭捕獲すれば総頭数は7000という状況が再現される事になる。 総頭数が7000頭以外の場合には、毎年の増加分はこの210頭より少ないので、従って、このレベルで捕獲を続けていくのが、もっとも効率よく安定した生産を続ける事ができるわけである。 また、捕獲量を210頭より少なく設定すれば、捕獲を続けていながら頭数も当初の10000頭に向けて徐々に増えていく。
以上が1931年にイギリスのラッセルによって提唱され、その後の漁業資源管理に大きく影響を与えたMSY理論の考え方の概要である。 無論、実際の捕獲においては捕獲するクジラの雄と雌の比率や年齢なども考慮に入れるなど複雑な要素が入ってくるし、現実の自然界では、捕獲を開始する前だからといって資源量が安定しているとは限らないのだが、基本的な考え方は以上のようなものである。
余談だが、IWCの歴史においてこのような考え方を鯨種ごとに当てはめて捕獲枠を設定したのは1970年代半ばからであり、また南氷洋のシロナガスクジラでは、このMSY理論が出るのとほぼ同じ(すなわち、まだ普及していない)1930/31シーズンに年間3万頭弱の捕獲が行われてピークを迎えている。 ちなみに当時の南氷洋捕鯨はノルウェーとイギリスがメインであり、日本が参加するのは遅れて1934/35シーズンからであった。 よく反捕鯨団体の主張を見ると、商業捕鯨を再開させたら今世紀始めのような乱獲状態に逆戻りする、という類の文を見かけるが、誇大妄想の感が強く、また捕鯨の資源管理の歴史に疎い一般市民をターゲットにしたプロパガンダと言っても良いと思う。
さて、実際の例で見ると、例えば、コククジラ(Gray whales)の北東太平洋系統群は、初期資源は30000頭程度と考えられているが、19世紀半ばからの過剰な捕獲によって20世紀初頭までには2000頭程度までに減ったと考えられている。 その後資源は保護されたが1960年代終りから1980年代終りまで、回遊ルートの西側にあたるロシア沿岸で原住民のために年平均174頭捕獲されても、年3%以上の増加を続け、その後も年間100数十頭の捕獲を続けながら1996年にはMSYレベルより若干高いレベルにあたる24000頭程度まで回復している。 MSYの推定値は670頭で、これは現在の頭数の3%程度に当たり、一方、原住民に許可された捕獲頭数は年平均で140頭程度にすぎないから、今後も増えていく事が期待できる。
また、ホッキョククジラ(Bowhead whales)も同様で、初期資源量が10000から20000頭程度と推定されるべーリング海系統群は過剰な捕獲によって激減し、1980年頃には3000頭程度だったが、その後、原住民生存捕鯨で年間40頭程度の捕獲を続けながら、現在では8000頭以上にまで増えてきている。 最近の研究では、資源量はMSYレベル近くまで回復してきており、年間100頭以上捕獲しても、なお増加し続けると考えられている(IWC 1998)。
さて、商業捕鯨の最後の頃に日本が南氷洋で捕っていたミンククジラの場合、状況はどうであろうか? まず、上の議論はそのまま単純に適用できない。 これはどういう事かというと、南氷洋のミンククジラの初期資源量は、今現在の推定資源量の76万頭をはるかに下回るせいぜい20万頭程度というのが大方の科学者の見方で(日本が本格的捕獲を始める直前の1971年当時、IWC科学委員会による推定資源量は15万頭から20万頭で推定MSYは5000程度であった。ただ、この時点ではIDCR調査航海は始まっていない)、つまりシロナガスクジラなどのようにオキアミというエサをめぐって競合する他の大型種が捕獲で激減しために、エサをめぐる環境が好転してしまい、商業捕獲を開始する前にすでに数が当初より増えていたと考えられるからである(これは、今世紀前半からのミンククジラの妊娠率の増加や性成熟年齢の低下、成長曲線の経年変化などから考えられる)。 南氷洋でのシロナガスクジラなども含めた捕鯨が始まる前のミンククジラ資源量を基準に考えるべきか、それともミンククジラの本格的な捕獲が始まった1970年頃の資源量を「初期資源量」と見なすべきかは、素人の私には判らない。 実際IWCでも新管理方式(NMP)という方法で捕獲枠を設定していた1970年代半ば以降では、1970頃のミンククジラ資源量は初期資源量と見なせないとして、毎年の増加量(Replaceent Yield - RY)をもとに捕獲枠を決めていた。 商業捕鯨が一時停止してから10年以上経つが、今仮に、「今現在の頭数を減らさない」事を指針にしたとすると、調査によって判っている年間5%前後という増加率と76万頭という90年代初頭の推定量から考えても、万単位の捕獲枠が出てくる。 ただ、現在IWCで採用されている改訂管理方式(RMP)は「超」慎重に控え目な数字を出すように設計されているので2000頭程度の捕獲枠しか出てこない。 ミンククジラだけの事を考えているなら、これはこれでけっこうだが、シロナガスクジラを早く回復させたい野心家(?)には、生態系のバランスを更にミンククジラ有利に傾けかねない危ない数字に映るかもしれない。
このように、10000トンの埋蔵量がある鉱脈から毎年100トン採掘すれば100年で枯渇するのと違い、生物資源の場合には上手に利用すれば持続的に利用し続ける事が可能なわけである。
(2000年5月13日 更新)
_