中国が日本人にやった暴虐 ←先日のエントリー記事
近代デジタルライブラリーへのリンク
『支那怖るべし : 急迫化する日支関係!成都・北海事件の真相』
斎藤二郎・著 今日の問題社 1936年発行
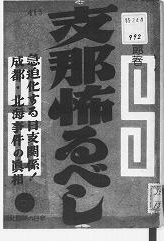
少し書き出してみます。( )内は私が付けた注釈。
先日取り上げた戦前(1930年代)出版された中国関連の本について詳しく見ていきます。
中国が日本人にやった暴虐 ←先日のエントリー記事
近代デジタルライブラリーへのリンク
『支那怖るべし : 急迫化する日支関係!成都・北海事件の真相』
斎藤二郎・著 今日の問題社 1936年発行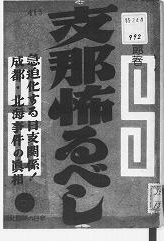
少し書き出してみます。( )内は私が付けた注釈。
「排日テロに緊張せる日支関係」より
南京政府(蒋介石政権)は年増芸者の如き心にくき手くだを弄する。その手管に、これまで日本はのせられて、支那の親日的部面を見ようとして来た。だまされ通して来た。もう怒ってよいのだ、怒らなければならぬのだ。長続きする怒りかたをせねばならんのである。
簡単に『断乎膺懲』(だんこようちょう・懲らしめること)というが、常に長続きせず支那人の涙や、後ろへ向いて舌を出す支那の笑顔に、寛大な日本は支那を見直そうとする悪癖がある。こんな事をしている間に支那は統一し強力となり、その力が懸命に排日に磨かれて来たのである。
かかる日支関係の切迫感の直接原因は成都、北海の両事件である。両事件は排日支那の正体を裁断して示したようなものである。
(逃れた日本旅館にて)
「自分らの存在が不満ならば、明日成都を去ってもいい」と釈明これつとめ漸くその中学生が納得したと見えて、室外で大群衆の暴徒を阻止せんとした気配が感じられた。だが既に悪鬼の如く狂って旅館を破壊した群衆は勢いに乗じて、血を見なければやまぬ情勢であり、午後6時40分ころ、終に歓声を上げながら一行の部屋に飛び込んだのである。
そして一行を部屋の片隅に押しつめ、全く袋の鼠のようにしてしまって、先ず先頭の瀬戸君に向かって顔面をなぐり、足で下腹部を蹴り、髪を引っ掴み、棍棒で頭部を強打せんとするなど、あらゆる暴行をやり、他の一団は渡辺君を取り巻き、あるいは深川、田中両君に迫ってありとあらゆる暴行を加え始めたのである。
この物凄い群衆の勢いに瀬戸君は血路を適宜に求めんとして、群衆に引きづられながら室外に飛び出した。
瀬戸君の話しによれば、その時渡邊君は机の脚をもぎ取って血みどろになって民衆と戦い、深川君は実に何とも言えない死の悲鳴を上げて、ソファの間にぶっ倒れたということである。
瀬戸君は室外に飛び出したが、もうその時は陽がとっぷり暮れて真っ暗闇、群衆の一人が真正面から照らす懐中電灯で、目がくらくらとする所を更に群衆に殴打される。
その中に洋服は取られ時計は引きちぎられ、万年筆、靴、ズボン、シャツ、猿股まで、奪い取られて殆ど裸体にされて3階から下へ下へともみくちゃにされながら引きづり出されたのである。
この時旅館の一帯の群集は1万人に達していたが、瀬戸君は旅館の前に飛び出して左にかすかに見える灯りを頼りに駈け出したのである。
(その後、道々に殴られ足を掬われながらも公安局に辿り着く)
(同じく公安局に逃げようとした田中氏は)幾度か群衆の棍棒の的となって昏倒し、小学生のため電気のコードでうしろ手に縛られて、旅館の左に方に引きづり出され、終に5回目の昏倒で立ち上がれなくなったのである。
(これを死んだと思い込んだ群衆は打つ手を止め命は助かった)
渡邊、深川の両君のその後であるが、渡辺君は群衆を相手に死を決意しての最後の活動を繰り返している間に、全身に打撲傷を受け、顔面を殴打されて血みどろになり、瀬戸君と同様身につけたものを尽く掠奪されて、棍棒を振り死の叫びをあげながら、旅館の前に現れ出たのである。
そのとき外は既に真っ暗闇、折から降り出した雨の中に怒涛の如き群衆を相手に最後の死闘をなさんとあたりを睥睨しているさまは凄惨そのものであったということである。
両君はそこで又々群衆のために殴られて半死半生の状態で旅館前を右側に折れて、旅館とほど遠からぬ正府街の一隅でついに立たず、悪鬼の如き群衆の打ち下ろした棍棒の一撃で怨みをのんでこの世を去ったのである。
深川君は旅館内において、暴徒の一撃に死の叫びを上げて、その場に昏倒したところ、群衆に後ろ手にしばりあげられて引きづり出され、あらゆる所持品を掠奪されて、半裸体のまま渡邊君の後に続いて(略)途中殴打されながら正府街の渡邊君の遺骸が放棄されてあった地点と程遠からぬところで惨殺されたのである。
私(大毎新聞社・田知花氏)は一刻も早く両君の遺骸に会見せんものと支那側に交渉して、ようやく午後6時ごろ正府街の火神廟というお寺にかけつけ、その一室に安置してある両君の遺骸に会見したのであるが、その死骸の惨忍な様相は、実に言語に絶することで、顔面は殆ど殴打されてそのあとかたを残さず、僅かに両君の身体の形によって両君の死体であることを確認せざるを得なかったほどである。
殊に渡邊君の死体は、最も凄惨を極め、その両眼は血にまみれて、天の一角を睥睨していたところを見ても、異郷万里の地に孤立奮闘のすえ、いかに同君が怨を飲んで死んだかが想像され、思わず悲憤の涙にくれざるを得なかったのである。
私をして言わしめるならば、惨殺犯人は両君の無数の打撲傷から言っても民衆1万がことごとく真犯人であり、もっとつきこんで言えば、この背後で糸を操る国民党部、ひいては国民政府が真犯人であるといわざるを得ない。
南京政権(蒋介石政権)は満洲、上海両事変をもって、この政策を具体化のチャンスとした。(略)
南京政権の支那統一に(抗日は)利用価値は充分である。
蒋介石はこの情勢によって排日政策の強化に自信を得たのである。
満州事変が起こるや彼は『日本の暴虐、日本の恐るべきこと』を宣伝した。
「日本と一戦をせねばならぬ」という空気が支那全土に起こって来た。
(蒋の言として)『日本とは無論一戦せねばならぬ。だが支那の現状では決して日本に勝てない。支那は一致団結して日本との戦いの準備をせねばならぬ、この準備のたえに先ず軍備の拡充を計らねばならぬ。真の愛国運動はまず軍備拡張から始むべきである』